「鉛筆の持ち方がぎこちない」「すぐ疲れてしまう」「筆圧が弱くて読めない」
そんな“書くのが苦手”なお子さんに戸惑ったことはありませんか?
発達障害や発達が気になる子どもの中には、書字に苦手さを感じやすい子が少なくありません
その理由は単なる「練習不足」ではなく、体の使い方・感覚・認知処理の特性に関係していることも
今回は、作業療法士の視点から「書くのが苦手な子」に対して家庭でもできる工夫を、5つの視点でご紹介します!
書字の困難は“がんばり不足”ではない
まず知っておいていただきたいのは、書字の苦手さは「やる気がないから」ではないということです
たとえば:
- 筆圧が弱い:紙にうまく文字が残らないので何度も書き直す
- すぐに疲れる:手や指の筋力や協調運動が未発達で持ちこたえられない
- 字が崩れる:体の中心が不安定で細かい動きに集中できない
こうした背景を無視して「もっと丁寧に書いて!」「集中して!」と繰り返しても、子どもにとってはつらいだけ
まずは“書けない理由”に目を向けた支援が大切です!
工夫①:筆圧が弱い子には“手の力を育てる遊び”を
筆圧が弱くて薄くしか書けない子には、手指や手首の力を育てることが第一歩です
“練習帳”よりも、楽しく遊びながら手を使う活動が効果的です
✅ 取り入れやすい遊び:
- 洗濯ばさみ遊び(指先で強くつまむ)
- 粘土やスライムをこねる・ちぎる
- 水の入った霧吹きを連続で押す
- 小さなビーズをつまんで仕分ける
- スポンジを絞って遊ぶ“洗濯ごっこ”
細かい筋肉や手首の安定性が高まると、自然と筆圧にも良い影響が出やすくなります
工夫②:“姿勢の崩れ”を見直すことで集中力が続きやすく
文字が崩れる・すぐに疲れる…そんなときには座る姿勢や机・椅子の高さもチェックしてみましょう
✅ 姿勢支援の工夫:
- 足の裏が床にしっかりついているか?
- 背もたれに寄りかかりすぎていないか?
- 肘が机の上にのって安定しているか?
- 姿勢保持が苦手な子には“足台”や“背当てクッション”の活用も◎
体幹が安定すると、手先への意識や集中力も高まりやすくなります
工夫③:書く道具や紙の工夫で“書きやすさ”を引き出す
子どもによっては、鉛筆やノートの種類を変えるだけでぐっと書きやすくなることもあります
✅ おすすめの道具例:
- 太め・三角軸の鉛筆(グリップが安定)
- 鉛筆に装着する“持ち方サポーター”
- 行間が広めの学習帳
- 書くスペースに色枠やマスがあるワーク
- ホワイトボード+マーカー(力を入れずに書ける)
「書きやすい」と感じる体験が、書字への抵抗感を減らす第一歩になります
工夫④:書く量を調整して“成功体験”を積む
書字が苦手な子どもに、毎回大量のプリントや漢字練習をさせると「できない」「つらい」という思いばかりが残ってしまいます
✅ 対応のコツ:
- 書く量を“半分”に調整してOK
- 「3文字書けたら花まる!」など小さな目標を設定
- 間違っても消しゴムで何度も消させない(疲れやすいため)
- 「口頭で答える」「シールを貼る」など書かない方法を取り入れる日も◎
“書けた”というポジティブな体験が積み重なることで、書字へのモチベーションも変わっていきます
工夫⑤:“書かなくても伝わる”経験も大切に
書字支援の最終的な目標は、「きれいな字を書くこと」ではなく、“自分の思いや考えを表現できること”です
✅ 書かない表現の例:
- お絵描きや写真カードを使って話す
- 音声録音で自分の考えを伝える
- パソコンやタブレットを活用して入力する
「字を書くのが苦手=表現できない」にならないように、その子に合った表現の手段を広げていくことも大切です
おわりに~書けるようになるまで“焦らず・比べず・寄り添って”~
書字の苦手さは目に見えやすい分、「○○ちゃんはもっと書けるのに」と比べてしまいがちです
でも、お子さんががんばっている姿・ちょっとずつでもできるようになったところを見つけて、「できたね!」と認めていくことが何よりの支援になります
ご家庭でできる支援はたくさんありますが、必要に応じて発達支援センターや作業療法士など専門家に相談するのもひとつの選択肢です
お子さんの「書けた!」「できた!」を、焦らず一緒に積み上げていきましょう!
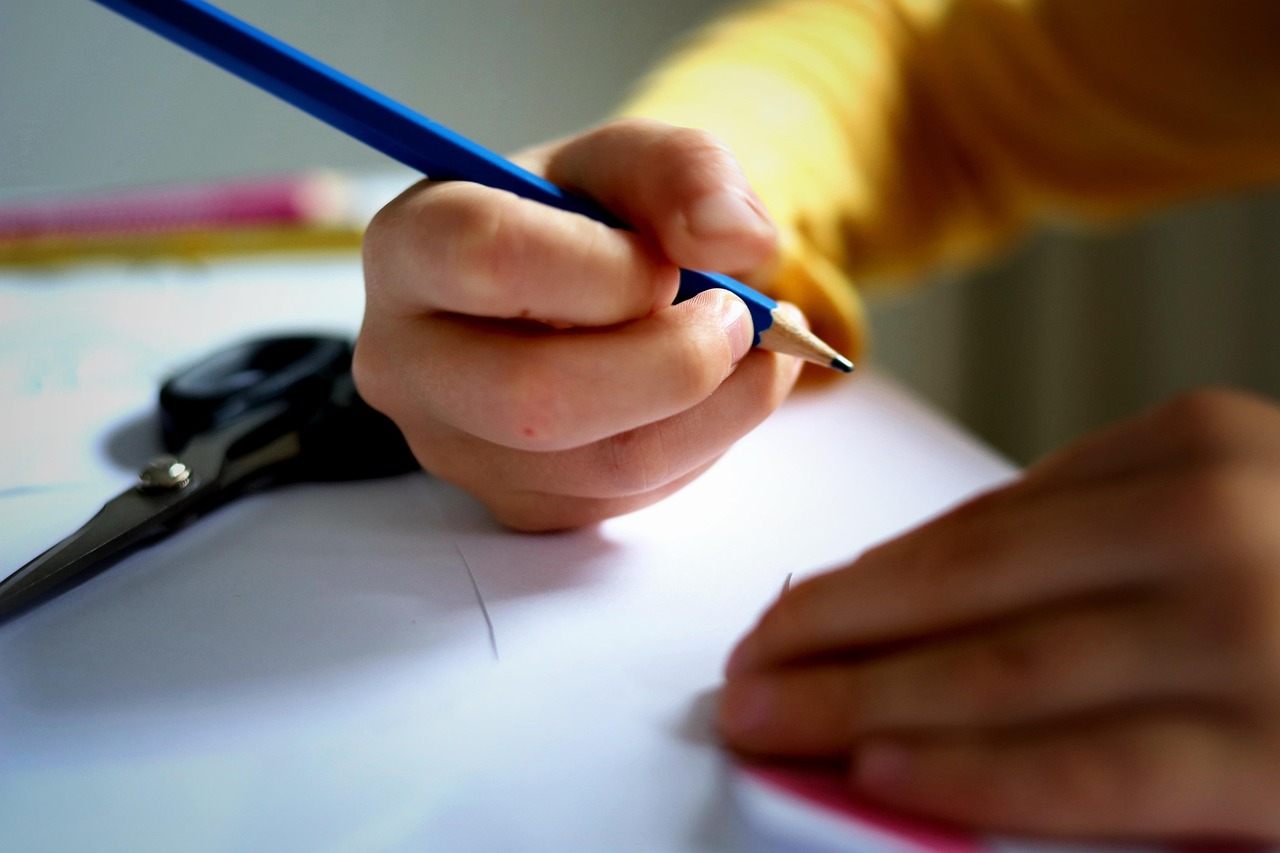


コメント